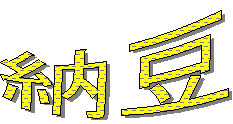

日本の伝統食“納豆"。独特のにおいとネバネバで好き嫌いの分かれる食品ですが最近は、健康食としての評価が高まっています。
納豆は日本古来の食べもの。
煮た大豆をわらに包んで、納豆菌で発酵させる納豆は、日本独自の食べもの。いつごろできたのかを伝える正確な記録はなく、その誕生には諸説があります。いずれも煮た大豆とわらとの出合いがきっかけ。なかでも、武士が馬の背にのせて運んだ、わらに包まれた馬糧の大豆が雨にぬれ、馬の体温で温められて納豆になったという説が有力です。大豆もわらもあった弥生時代には、すでに食べられていたともいわれます。
名前の由来はお寺の台所。
納豆の名前は、寺の納所(台所)で作られたことに由来します。肉食が禁じられていた僧侶にとって、納豆は貴重なたんぱく源だったのです。ただし、お寺で作られていたのは、中国から伝えられた糸を引かない納豆で、「寺納豆」と呼ばれるもの。どちらかというと、中国調味料の豆鼓に似ています。
普通、納豆と呼ばれるのはネバネバと糸をひく「糸ひき納豆」。大きく分けて、大豆を丸ごと煮て納豆菌で発酵させた「丸大豆納豆」と、大豆を妙って粗くひき、表皮をとり除いてから煮る「ひき割り納豆」とがあります。
原料の大豆を上回るパワー。
原料の大豆も栄養価の高い食品ですが、納豆は納豆菌の働きでそのすぐれた栄養成分がさらに吸収されやすくなっています。とくに、パワーを発揮するのが美肌を作り。たんぱく質をはじめ、ビタミンBやE、レシチン、サポニンなどの成分が、肌を若々しく保つのに効果的です。
その他、ネバネバ成分のナットウキナーゼは血栓防止、発酵の過程で作られるビタミン・Kは、カルシウムの吸収を助けて骨粗鬆症予防に役立つなど、納豆ならではの作用も注目されています。
おいしく食べるには?
納豆にはねぎと辛子が一般的ですが、わさびやしょうが、青じその葉、のり、削りかつおなど、薬味を変えるとおいしさが広がります。若い人にはマヨネーズも人気。ネバネバが少なくなり、においも気にならないとか。最近は、カレーに納豆をのせる“納豆カレー"が人気上昇中。納豆が苦手な子どもにも好評だそうです。
なお、納豆は比較的日もちしますが、時間がたつと白い粒が出てくることがあります。これは水に溶けないアミノ酸の結晶なので、食べても大丈夫です。
あおじはいかが 06/10